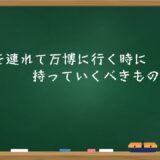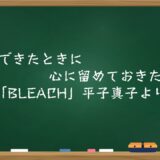おはようございます。ヨシパパです。
甲子園を見ていると、プレーをする選手たちよりもアルプススタンドで応援している補欠たちに目が行きます。
これは私自身が強豪校でスポーツをしており、かつ一度もレギュラーになったことが無いからだと思います。
約20年の運動部生活の内チームの代表として試合をしたことは1度たりともありません。
このような自身の経験から試合そのものよりも試合に出れないアルプススタンドの選手に慣れなかった部員に共感するのかもしれません。
さて、引退の時に「試合に出れなくても高校3年間厳しい練習についてきたことが一生の財産になる」的な事を言われた記憶がある方も多いのではないでしょうか?
私自身中学でも高校でも同じようなことを言われた経験があります。
その時は美談として自分を納得させていました。
しかし、本当にそうでしょうか?
今回は補欠の経験が本当に役に立つのか考えてみました。
補欠の中にも幅があり、レギュラーと補欠のボーダー上にいる人もいれば、レギュラーにかすりもしない補欠もいるかと思います。
私の場合は後者であり、学校や部活によって大きく変わるかと思います。
共感していただける方や、まだ優しい、もっと厳しいと感じる方もいらっしゃいますと思いますが、読み物として楽しんでいただければと思います。
- 理不尽に慣れる
強豪校の厳しい練習がメディアに取り上げられることがありますが、レギュラーと補欠ではその練習内容が違うことが多くあります。
よくあるのはレギュラーはグラウンドを使用している間、補欠はランニングのように分けられるパターンです。
ひと昔前だと1年はボールに触れないみたいなことがありましたが、私の場合3年でも補欠はボールに触れないことが多々ありました。
公式戦の前になると「私は陸上部に入ったのかな?」と錯覚するほど走ってばかりの時期がありました。
雨が降った際にはレギュラーのためにグラウンドの水抜きを行い、ミーティングが終わったときに使える状態にしたこともありました。
その時にレギュラーの方から「余計な事するなよ…」と言われたのは今でも忘れません。
このように補欠はやめられても変わりがいくらでもいるので、駒として使い捨てられます。
- 奴隷根性が身につく
上記のように運動そのもので貢献できない補欠はそのほかでチームに貢献しなければなりません。
球拾い、応援、偵察などチームに貢献しなければならないことは沢山あります。
これは何かしら自分の存在意義を示したいことの表れかもしれません。
ある種の生存本能でしょうか?
そうしている内に言われたことにはすべて「ハイ」で返すようになれます。
- うまくさぼる方法
他悦が練習するときに考えているのは「どうやったらうまくさぼれるか」です。
「どうやったらレギュラーになれるか」とは考えません。
それは目標が遠すぎるからです。
上を目指す向上心もなければやめる勇気もない為、いかにして今日の練習を効率よくこなすかを考えています。
コーチや監督に直接指導されることもない為、特に怒られることもなく練習をやり過ごしています。
「いてもいなくても一緒、むしろ害悪」というのが底辺の補欠です(ちなみに私もこれでした)。
会社員でいう窓際族のような考え方でね。
- 組織を背負う責任
強豪校になると100名を超える部員がいることもざらです。
その中で試合に出れるのは上位1割程度でしょう。
また、全国大会に出場となれば各都道府県の代表として試合をすることになります。
部員、学校、都道府県、予選で倒してきた相手、家族などを代表して試合をする重圧は補欠では絶対に味わうことができません。
当たり前のプレーが当たり前にできなくなるそんな重圧をはねのける経験はまさにレギュラーでしか体感することはできないのです。
- プレッシャーに打ち勝つメンタル
一打逆転のチャンス、決めれば勝ちのPK戦など運命が決まるような一瞬を任されたことはあるでしょうか?
そういったプレッシャーに打ち勝ってきた警官があるのがレギュラーの人間たちです。
補欠が練習でするものとはレベルが違います。
そういった大舞台の経験は補欠には絶対に理解できない感覚かと思います。
- 大舞台でのメンタルコントロール
大観衆の中でプレーすることは想像以上に緊張します。
甲子園で正面のゴロをエラーしてしまったり、送球がそれてしまったりというプレーが出てしまうのはそういった場の雰囲気になまれてしまっているのではないでしょうか?
おそらく選手たちは練習で何万回もそのプレーを練習し、成功し続けていると思います。
当たり前のプレーを当たり前にするメンタルを育てることができるのはレギュラーのみのスキルだと考えられます。
- 自分を追い込める習慣
強豪ともなると日々の練習はとてつもなく厳しいものになります。
練習が厳しいからと言う理由で、それまで有望とされていた選手が辞めてしまうこともしばしばあります。
その厳しい練習をどのように取り組むかにも差が出てきます。
私のような補欠の人間はいかにその厳しい練習はこなすかを考えます。
一方、レギュラーの人間は試合を想定したり、より厳しく負荷をかけて取り組みます。
つまり、練習メニューとしては同じでもそれに取り組む姿勢や負荷は全く別物と考えてよいでしょう。
特にレギュラーの中でも常に競争が発生しており、少しでも隙があればメンバーが入れ替わる厳しい環境にあります。
ここからは補欠の私が社会人になって役立ったスキルを紹介していきます。
- 社畜精神が身に染みている
社会に出ると理不尽なことが日常茶飯事で起こります。
自分のミスでもないのに取引先に謝らなければならなかったり、後輩のミスを怒られたりと自分に非の無いところで責められることは誰しも経験があるかと思います。
また、長時間の練習やスポットの当たらない作業に慣れているので、会社でも上司の指示に対して抵抗感なく取り組むことができます。
- サポート役に徹する
晴れ舞台の経験がない為、いわゆるエース社員や頼れる先輩になる器はありません。
一方で、厳しい縦社会にいた経験は先輩を立てることを自然とできるスキルがあります。
これは会社を生き抜く上で、出世はできないですが絶対に必要なスキルです。
人間だれしもそうですが自分の経験したことは良かったと思いたい生き物です。
それでいつまでも補欠の経験をよかったと思っている内は絶対に成長できません。
その経験を糧にして絶対にのし上がるというメンタルに切り替えることが補欠だった人間が社会人になったときに成功する秘訣だと思います。
もちろんレギュラーだから補欠だからと言って人生が決まるわけではありません。
一方で学生時代の経験は人格形成に大きく影響します。
それぞれの立場の考え方を把握することで自分に足りない考え方メンタルを補填できるようしましょう。
 30代4人家族で2000万円貯蓄したFPの財遊記
30代4人家族で2000万円貯蓄したFPの財遊記